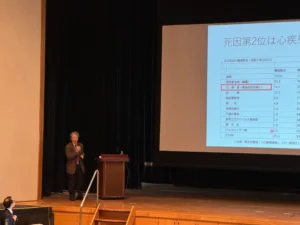介護の「気づき」が心不全の再入院を防ぐ—施設職員向け心不全講演会 開催報告
群馬大学医学部附属病院脳卒中・心臓病等総合支援センター
コラム 心臓病あれこれ
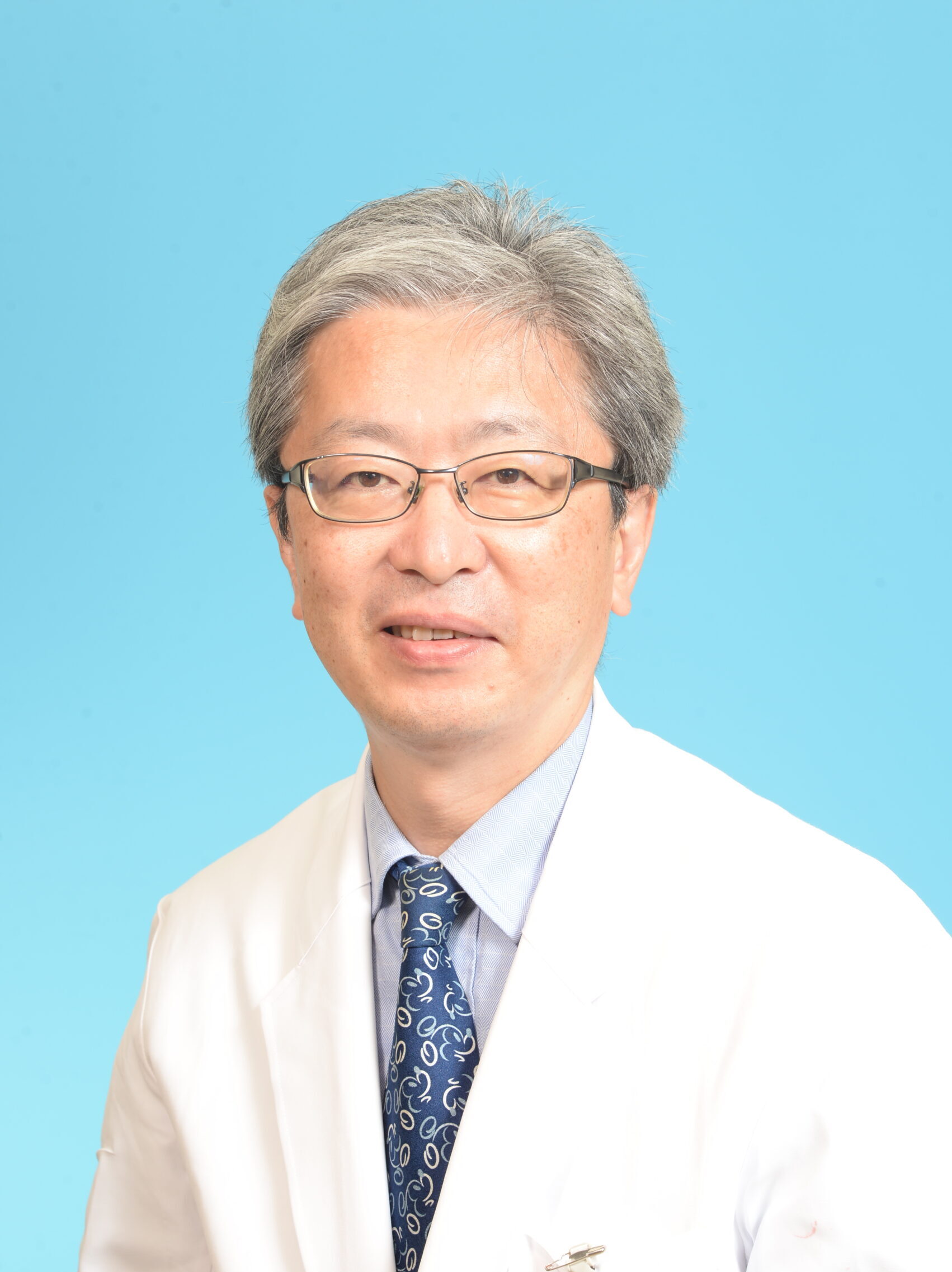
センター長
群馬心不全地域連携協議会メンバー 星野圭治先生(群馬県立心臓血管センター)は、医療スタッフや介護の方々に対して、心不全の理解を深めていただくべく、動画や教材の作成に数多く携われておられます。ぐんまのうしんでも、それらの動画を掲載しております。
星野先生は、今年になってから介護に関われる方に、自ら出向き講演をなさっておられます。令和7年8月20日には、渋川地区在宅医療介護連携支援センター主催(共催:群馬県介護支援専門員連絡協議会渋川圏域支部)の第17回介護職のための在宅医療講演会で、「高齢者ケアにかかわる全ての方に理解していただきたい心不全の病態と観察のポイント〜心不全患者さんへの質の高いケアを目指して〜」というタイトルでお話しされました。その抄録を掲載いたします。このような内容について、あるいは心不全に関する講演会や市民公開講座の講師派遣の希望がありましたら、是非群馬心不全地域連携協議会までご連絡ください。
本活動には、ぐんまのうしんも協力しております。全県で、さまざまな方が関わり、この輪を広げることができればと考えております!
介護の「気づき」が心不全の再入院を防ぐ—施設職員向け心不全講演会 開催報告
群馬県立心臓血管センター 星野 圭治
平素より、群馬心不全地域連携協議会の活動にご協力いただいている群馬県医師会の先生方に、心より感謝申し上げます。
背景と目的
心不全患者は全国的に増加しており、いわゆる「心不全パンデミック」は社会問題になりつつあります。救急・入院医療だけでの対応には限界があり、入院から外来、病院から在宅、そして介護施設へと続く“移行期”において、日常の観察を軸にした切れ目ない支援が求められています。介護施設に入所される慢性心不全患者さんも多いのが実情です。こうした必要性を踏まえ、群馬心不全地域連携協議会は、地域の実情に根差した連携を進めるとともに、現場のニーズに応じた学びの場を提供しています。今回の講演会も、その一環としてお話させていただきました。
開催概要とねらい
令和7年8月20日、渋川地区在宅医療介護連携支援センター主催(共催:群馬県介護支援専門員連絡協議会渋川圏域支部)の第17回介護職のための在宅医療講演会に登壇し、「高齢者ケアにかかわる全ての方に理解していただきたい心不全の病態と観察のポイント〜心不全患者さんへの質の高いケアを目指して〜」についてお話しする機会をいただきました。会場には約100名が参加し、Googleフォームで寄せられた事前質問に基づいて双方向の議論を行い、特別な検査に頼らず、体重変化や息切れなど日常から得られる「生きた情報」をどのように拾い上げ、日々のケアや医療連携につなげるかを共有しました。
日常観察が再入院を防ぐ
心不全は悪化と安定を繰り返す慢性疾患であり、その悪化のサインは、足のむくみ、動作時の息切れ、数日での体重増加といった小さな変化として現れます。介護の現場は利用者と最も近い距離にあり、こうした変化に最初に気づき得る立場にあります。慢性心不全を持つ入所者について、介護の現場で気づいた時点を記録し、共有し、必要な連絡や対応につなげれば、再入院を避ける機会は確実に増やすことが出来ます。介護施設職員が心不全管理の最前線に立っているという共通認識を、参加者の皆さまと再確認することができたと考えています。
三局面(入所直後・維持期・急変時)の実践ポイント
講演では、利用者の状態を「入所直後」「維持期」「急変時」という三つの局面で捉え、観察と対応を現場で実行しやすい形に整理しました。入所直後は、既往や増悪要因、服薬状況を確かめ、基準体重と最初の浮腫・労作時息切れの状態を明確に記録します。維持期は、むくみ・息切れ・体重増加の三点に常に目を配り、減塩の工夫(調味料を本人任せにしない等)や軽い運動、ワクチン確認を無理なく続けます。薬剤では、高齢者で起こりやすい注意点として、β遮断薬で遅れて徐脈が出る場合があること、SGLT2阻害薬では食欲低下や脱水・尿路感染時に一時休薬の判断が必要になることを共有しました。心不全診療における治療の進展は目覚ましい一方で、日々の生活で重視すべき基本は大きく変わりません。どれほど有効性が示された薬剤であっても、きちんと継続して内服されなければ効果は発揮されず、意味をなしません。観察・記録・共有と服薬支援という足元の実践が、最新の治療を「生きた治療」に変える要です。急変時は、横になれない息苦しさ、血圧低下、意識の変化、唇や指先のチアノーゼ、低酸素血症といった警報所見を見逃さず、バイタル測定と迅速な連絡、医師の指示に基づく初期対応へつなぐ基本動作を確認しました。また、講演会の最後では協議会が作成した「心不全健康管理手帳」も紹介し、体重・症状・服薬を一体として捉える実用的なツールとして活用を促しました。
ガイドライン・学会の動向と地域の共通言語
介護施設のスタッフによる心不全ケアの強化は、2025年改定の心不全ガイドラインが示す多職種連携の強化やセルフケア支援の方向性と一致しています。2025年10月に鳥取で開催された第29回日本心不全学会学術集会においても、入院から外来、病院から在宅、そして介護施設への移行期医療における、切れ目のない移行期ケアの重要性が複数のセッションで取り上げられており、地域全体で共通言語と共通手順を整える必要性が再確認されました。新たな作業を増やしたり、費用のかかる検査を行うのではなく、「いつもの観察と記録」を確実に行い、異常が見られた時点で早めに相談・対策を行う知識を共有すること、その流れを整えることが重要であると考えられます。
今後の予定と連携の方針
前段で述べたとおり、心不全パンデミックに対応するには、地域の日常的な関わりの中で悪化の兆候を早期に捉える仕組みが不可欠です。とりわけ移行期では生活環境の変化を最小化し、小さな「気づき」を確かな行動につなげることが再入院の予防と生活の安定に直結します。今後については、地域ごとの資源や特性を生かした活動を続けつつ、現場の需要に応じて勉強会や講演会を機動的に行い、県全体の心不全診療を後方から支えていきたいと考えています。直近では、11月に沼田利根医師会地域医療センター講堂において、同趣旨の講演会の機会をいただいております。群馬心不全地域連携協議会は「県民が心不全で苦しまない県」を目標に、地域の特性を生かしつつ、需要に応じた講演会や現場向けの学びの場を通じて、県全体の心不全診療をしっかりと支えてまいります。地域の皆さまとともに、切れ目のない心不全ケアを一歩ずつ広げていきたいと考えています。