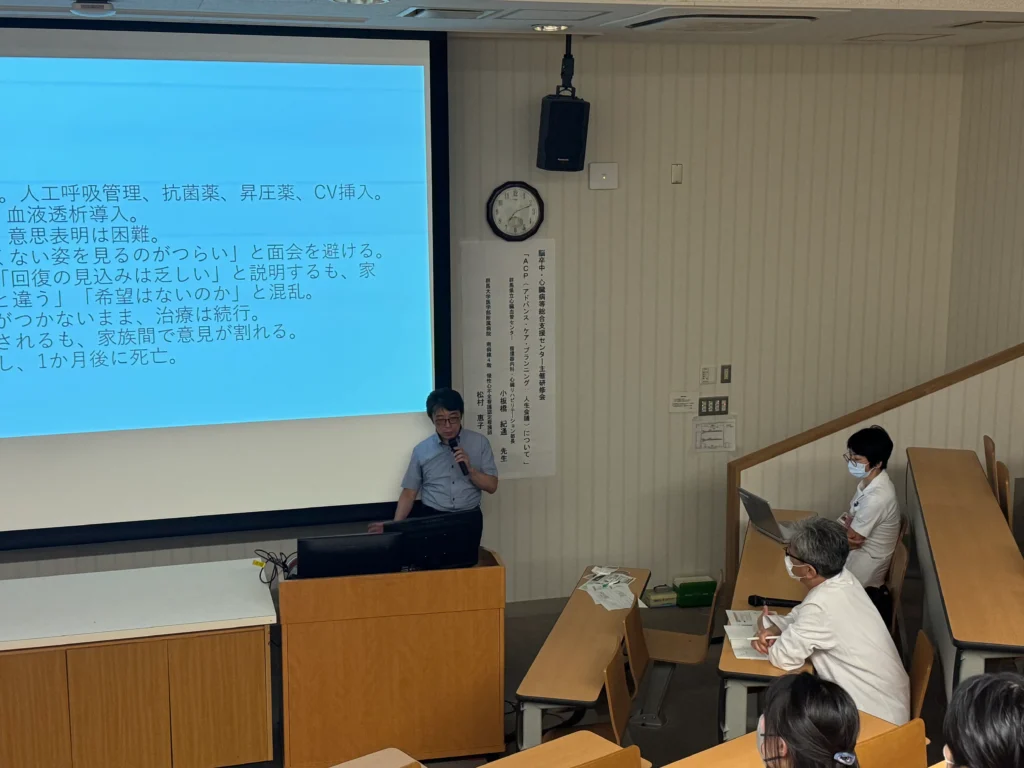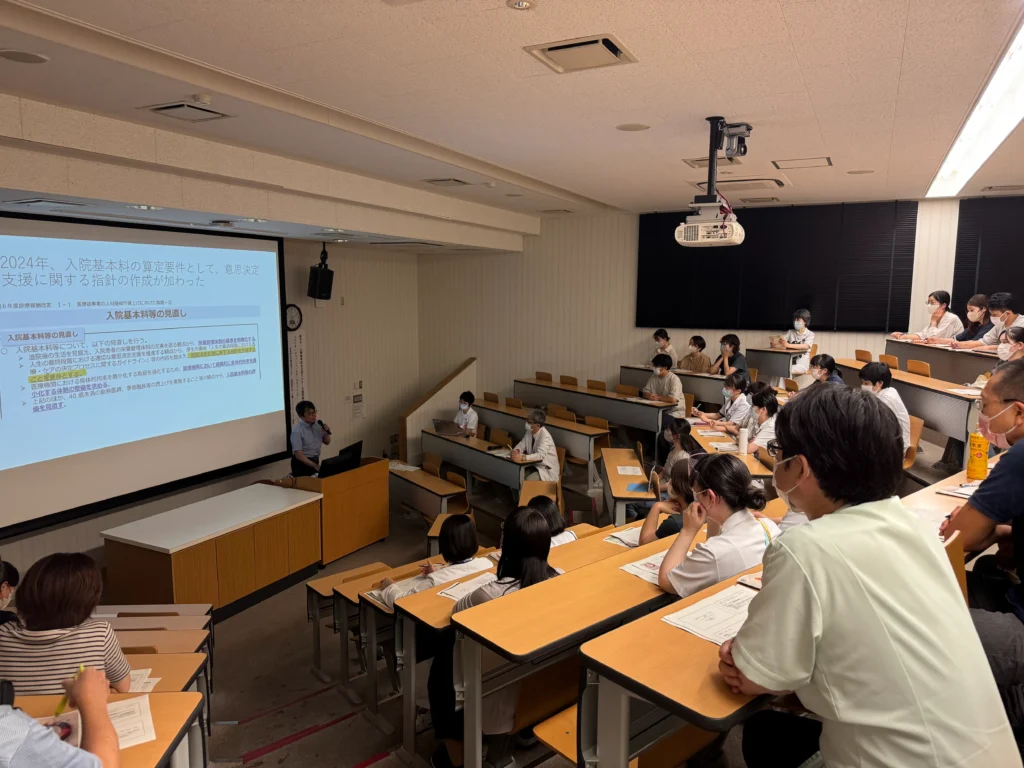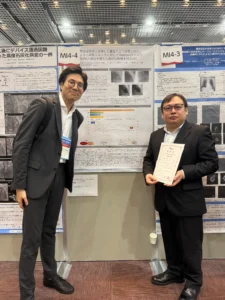7月9日に本センター主催ACP(Advance Care Planning)講演会を開催いたしました。
7月9日に本センター主催ACP(Advance Care Planning)講演会を開催いたしました。
ぐんまのうしんでは令和6年度に4回のACP関連講演会・勉強会を行ってまいりました。そして、群馬大学附属病院では、4月の臨床倫理委員会委員会において循環器疾患患者さんに対して「いきかたノート」を用いてACPを実践することを許可いただき、循環器内科の外来並びに病棟で実践を開始しました。

そのような背景のもと、7月9日ぐんまのうしん主催本年度はじめてのACP講演会を行いました。
今回はお二人の講師(小板橋紀通先生、松村恵子看護師)から、大変有用なご講演をいただきました。
・小板橋紀通先生「高齢者心不全治療と人生会議(ACP)―そのひとらしさを考えて―」
ACPとは何か?という基本的なことからご説明があり、DNARはACPと同義ではないことなど含め、特に日常現場でも誤解があるようなことについて解説いただきました。
そして、人生会議の重要性をご説明いただき、患者さんに寄り添うコツを教えていただきました。ACPというと、どうしても「どうやって死を迎えたいか」という何となくネガティブなことが前に出てきそうですが、患者さんの病気との向き合い方やご希望を知る段階で、今やってみたいことは何でしょうか?ということを聞いてみることも大きな情報を得る意味で大事なことであるということでした。患者さんが自分の死をまったく意識しない状態で突然話をするのはうまくいかず、心の準備(レディネス)ができているかを確認しつつ、段階的に話をすすめていくことが重要であること、また、病状の時期により考え方も変わるので、時間をおいて何度か確認することも必要であること、その中で「いきかたノート」が大いに役立つということも含めてお話しいただきました。
昨年お呼びした栁川先生からもお話があったように、世の中に死んだことがある人は生きていません。むしろ一例として「来年の今頃元気だった時にどんなことがやりたいのか」という質問を聞く中にも患者さんのいきかたを知るヒントがあることを我々は再認識する必要があると思いました。
・松村恵子看護師「循環器疾患患者に「いきかたノート」を使用してー看護師の視点ー」
松村さんは、日本循環器学会認定心不全療養指導士の資格を早いうちから取得され、ぐんまのうしんでも中心的な活躍をしてくださっています。そして今回話題の「いきかたノート」作成にも携わってきた経験があります。
講演では、いきかたノートを倫理委員会で使用することをお認めいただいてから、循環器疾患患者さん8名に対しての使用経験を中心に、良かったことや今後改善すべき点を含めてお話がありました。特に、2名が反省と要検討な事例であった点については深く考察もいただきました。看護師さんなら接する時間が医師と比較して長く、距離感が身近であるため、医師では聞くことができない患者さんからの深い話も聞けることも多く、その中で患者さんのご希望をくみ取ることも可能ではないかということもお話しいただきました、
河村恵美看護部長さんからは、この取り組みを院内で様々な疾患でも広げる取り組みを行うよう引き続き努力してほしいという激励の言葉も頂戴しました。
今回の講演会では、院内だけでなく、院外からも多くの方にご参加いただき、様々な議論を行うことができました。ACPをどうやって行うかについて、正解はないと思いますが、皆さんと議論する中で少しでも理想に近づく形に持って行けることができればと思います。また、このような活動を通じて、緩和ケアセンターとともに群馬大学医学部附属病院において循環器疾患だけでなく様々は疾病に対するACP活動にもつなげていくことができればと考えております。引き続きご指導ご鞭撻をお願いいたします。